ケイスケ@MBTIコーチ ======!特集記事!======
MBTIのタイプ診断に興味を持って、
のように、
- 「自分のことをもっと知りたい!」
- 「これは当たってる、これは当たってない!」
「ちょっとした性格診断」程度に自分のタイプに関する情報を見ていると…
むしろ”逆効果”になり、
自分の才能・可能性がどんどん潰れていく…という”不都合な真実”、知っていましたか?
>>MBTIの不都合な真実と、人生を壊す最悪の罠とは?



そんな悩みや疑問を本記事で解決します!
子育てにおいて、
自分の性格が子どもに与える影響って気になりますよね。
共感力が高く、感受性豊かなINFPは、
実は「毒親になりやすい」なんて言われることも。
そんなことを聞いてしまうと、
知らず知らずのうちに子どもを傷つけていないか、
不安になる方も多いと思います。
そこでこの記事では、
INFPが毒親と言われる理由とその解決策を徹底的に解説します!
- 毒親の基本特徴
- INFPが毒親と言われる理由9選
- INFPのための毒親セルフチェックリスト
- INFPだからできる!健全な親子関係を築く9つのヒント

よりよい親子関係を築きましょう!
目次:クリックで開きます→
毒親ってどんな親?主な特徴5つ

近年「毒親」という言葉を耳にする機会が増えてきました。
「毒親」とは、子どもに苦痛を与え、
成長に害を及ぼすような親のことを指します。
具体的にどんな親なのか、
ここでは5つの主な特徴を簡単に見ていきます。
- 過干渉:子どもの行動を管理し、友人関係や趣味にまで細かく口を出す
- 過保護:必要以上に甘やかしたり、子どもの問題を親が解決したりする
- 依存:子どもに「自分の幸せ」や「生きがい」を託してしまう
- 無関心:子どもにまったく関心を持たず、育児を放棄する
- 支配的:子どもを自分の思い通りになるよう、過剰にコントロールする
これらの特徴を聞くと、
「自分には当てはまらない!」と思うかもしれませんが、
どんな家庭にも多少の要素が潜んでいる可能性があります。
ぜひこの記事を、自身の子育てを振り返るきっかけにしてみてください。
INFPが「毒親になりやすい」と言われる理由9選

「毒親」の特徴とINFPの性格パターンには、
どのような繋がりがあるのでしょうか。
ここでは、INFPが「毒親になりやすい」と言われる理由を、
9つ紹介します。
- 高い理想を子どもに求める
- 共感力の高さによる過干渉
- 感受性が強く感情の起伏が激しい
- 内向的な性格ゆえの社会性の欠如
- 現実問題からの逃避傾向
- 完璧主義が招く子どもへのプレッシャー
- 子どもと深い関係を求めて依存する
- 平和主義から子どもとの衝突を恐れる
- 口下手によるコミュニケーション不足
理由①高い理想を子どもに求める
INFPは自分の理想を大切にするあまり、
無意識のうちに過度な期待を子どもに求める可能性があります。
「子どもにはこうなってほしい」という信念が強く、
またそれは善意からくるものなので、
子どもの意志とのギャップに気がつきにくいからです。
たとえば、
- もっと勉強して○○大学に進学したらどう?
- 一生安泰になる○○のような職業に就いてほしいな
- あなたらしさを分かってくれる子と友達になったら?
- 人の気持ちを大事にする子になってね
など、勉強や進路、友人関係、価値観にまで、
自分の理想像を子どもに押し付けてしまうことも。
このような言動が続くと、
子どもの自己肯定感が低くなったり、
子どもが自分のペースで成長する余地を狭めてしまう危険があります。

親なりの価値観を伝えることは大切ですが、過度な期待はプレッシャーに。
結果として、子どもは自由や自立を阻害されたと感じやすくなるのです。
理由➁共感力の高さによる過干渉
INFPの大きな特徴である共感力。
一見すると理解のある親に思えますが、
それが行き過ぎると「毒親」としての一面を見せることがあります。
なぜなら、子どもの感情に入り込みすぎて、
親が過度に干渉してしまうことがあるからです。
具体的な例を3つ挙げます。
- 子どもがつらいと自分もつらいと感じやすい
⇒早く解決しなきゃと思い、子どもが整理する前に問題を片づけてしまう - 子どもの些細な気持ちの変化を敏感に察知する
⇒子どもが言語化する前に、勝手に先回りしてサポートしてしまう - 子どもの失敗を自分のことのように思う
⇒失敗を避けるために、子どもの選択に口を出してしまう
優しすぎるがゆえの過干渉ですが、
子どもは自分の意思や自立性が尊重されていないと感じることも。

ストレスと反発心を生むこともあると覚えておきましょう。
理由③感受性が強く感情の起伏が激しい
INFPは感受性が極めて高く、
日々の出来事に強く感情が揺さぶられることから、
「毒親」になりやすい傾向があると言われます。
親の感情の起伏が激しいと、
子どもにとって戸惑いや恐怖の元になりやすいからです。
たとえば、
- 子どものちょっとした一言や態度に、強く反応してしまう
- 普段は怒りを我慢しているが、限界を超えると感情が爆発してしまう
- 子どもの些細なトラブルや悩みにも、過剰に対応してしまう
など、子どもにとって不安定な環境を与えることがあります。
ただし、全てのINFPの親がそうとは限りませんし、
感受性が強い分、愛情表現が豊かである側面もあります。

感情のコントロールが重要となるでしょう。
理由④内向的な性格ゆえの社会性の欠如
INFPは内向的な気質が強く、
家族やごく親しい人間関係で満足しやすいタイプです。
この内向性が過剰に偏っている場合、
親の「毒性」につながる可能性があります。
なぜなら、親が自分の殻に閉じこもってしまうことで、
子どもも窮屈な環境に身を置くことになるからです。
ここでは、INFPの内向性が、
子どもに悪影響を与える例を3つ挙げます。
- 親が自分の世界に閉じこもりすぎる
⇒子どもは親の意識のなかに入れず、遮断されたと感じる - 学校行事や地域交流など、社会的な関わりを避ける
⇒子どもの社会性の発達を阻害する - 外の世界とのつながりが薄く、子どもが親のすべてになっている
⇒子どもへの支配や依存の傾向が高まる

危険性を理解して、子どもの成長環境を拡げる姿勢が大切です。
理由⑤現実問題からの逃避傾向
夢や理想に生きるINFPは、
現実世界の厳しさや困難に向き合うのが苦手な傾向があり、
それが「毒親」と見なされる一因に。
なぜなら、子育てにおいて生じる困難な問題と向き合うことを避けていると、
子どもが放置されていると感じてしまうこともあるからです。
たとえば、下記3つのような行動により、
子どもに悪影響を及ぼす可能性があります。
- 子どもの現実的な問題になると、話をそらしてしまう
⇒子どもは「自分の話は大切にされていない」と思いやすくなる - 「きっと大丈夫」と理想に逃げ込んでしまい、問題を積極的な解決しようとしない
⇒子どもが問題を自分ひとりで背負い、追い詰められてしまう - 対立や衝突を避けたい気持ちから、子どもが抱える問題に気が付かないフリをする
⇒親としての健全な機能が失われる可能性がある

子育てにおいては現実としっかり向き合う姿勢も不可欠と言えるでしょう。
理由⑥完璧主義が招く子どもへのプレッシャー
INFPには「完璧主義」に近いこだわりを持つ人も多く、
子どもに対しても完璧な振る舞いや結果を求めてしまう場合があります。
こだわりが行き過ぎると、
知らないうちに子どもの自己肯定感や自立心を阻害してしまいます。
なぜなら、子どもがいくら頑張っても不十分だと感じやすく、
「失敗=悪いこと」と感じるようになるからです。
さらに、「できない自分」への劣等感を抱きやすくなります。
たとえば、無意識のうちにこんな言葉をつかっていませんか?
- 「あなたならもっとできると思っていたのに」
- 「何でわからないの?もっとよく考えて行動して」
- 「せっかくのチャンスだったのにもったいないね」
行き過ぎた完璧主義は子どもへのプレッシャーを増長させ、
緊迫した親子関係になることも。

理由⑦子どもと深い関係を求めて依存する
INFPの親は、その愛情の深さや共感力の強さから、
子どもに心理的依存をしやすい傾向があります。
心理的依存は、特定の状況下では子どもにとって重荷になるかもしれません。
無意識のうちに、
度が過ぎた「心の支え」や「生きがい」を託しすぎてしまう可能性があるからです。
INFPの親が子どもに依存する背景と、
子どもへの影響を3つ挙げます。
- 自分の理想的な生き方を子どもの成長に託す
⇒子どもは親の夢を生きているように感じ、自分の感情がわからなくなってしまう - 孤独や自信のなさを子どもの存在で埋めようとする
⇒子どもは自分の自由よりも、親を喜ばせることを優先してしまう - 成長して自立しようとする子どもを、「寂しい」と引き止めがちになる
⇒親子の心理的な自立が育たなくなる
INFPは、子どもとの心のつながりや一体感を強く求める傾向があり、
この強い絆への憧れが時に過度な依存に繋がってしまうことも。

理由⑧平和主義から子どもとの衝突を恐れる
INFPの平和主義な傾向は、
家庭に優しい雰囲気をもたらす一方で、
衝突を避けるあまり問題を表面化させにくい側面もあります。
なぜなら、INFPの親が持つ平和主義には、
深い理想と感受性に裏打ちされた、
「心の静けさ」と「調和」を重んじる姿勢があるからです。
平和主義が、
子どもに悪影響を与える具体例を3つ挙げます。
- 子どもとの衝突を避けるために、わがままを受け入れすぎている
⇒子どもは自分の欲求は全て通ると思い込み、自己中心的な考えを持つようになる - 注意したり叱ったりするべき場面で柔らかく伝えすぎる
⇒子どもは規範意識が曖昧になり、場合によっては親を見下すような態度になることも - 自分の感情を抑えすぎることで、ストレスをためている
⇒子どもは親の感情がわからず、常に顔色を伺っている状態になる
衝突を避けることで根本的な問題が解決できず、
子どもが「本音を話してくれない」と感じてしまうことも。

理由⑨口下手によるコミュニケーション不足
INFPは感情が深い一方で、
その感情を言語化するのが苦手な傾向があります。
この特徴は、時に毒親と言われる原因にもなり得ます。
なぜなら、子どもとのコミュニケーションが不足しがちになり、
子どもの心に影を落とす可能性があるからです。
例えば、親子間で言葉の不在が続くと、
- 親の気持ちが分からず、愛されているのか不安になる
- 自分も感情表現をしないことが正しいと思い込み、我慢が増える
- 悩みや不安を相談しづらくなってしまう
といった影響を子どもに与えてしまうことがあります。

口数は少なくても、誠実な態度や小さな言葉かけを重ねて、
コミュニケーションを取ることが大切ですね。
INFPのための毒親セルフチェックリスト

ここでは、子どもと向き合うなかで、
INFPがついついやってしまう行動10選を紹介します。
自分に当てはまる項目があるか、
行動を見直す指標のひとつとして、チェックしてみてください。
【INFPのための毒親セルフチェックリスト】
| No. | チェック項目 |
| 1 | 自分の理想像に子どもを当てはめてしまう |
| 2 | 自分が不安になると子どもをコントロールしたくなることがある |
| 3 | 子どもがつらそうなとき、「自分が悪かった」と責めすぎる |
| 4 | 子どもの成功や失敗が「自分の評価」のように感じることがある |
| 5 | 子どもと向き合うのがしんどいと感じ、無意識に避けてしまう |
| 6 | 感情が高ぶると、何も言わずに引きこもってしまう |
| 7 | 子供の成長に「まだ足りない」と完璧を求める |
| 8 | 子どもの選択に不安や抵抗を感じると、つい否定的になる |
| 9 | 子どもが自分から離れていくことに強い寂しさを感じる |
| 10 | 自分の癒しや心のよりどころが「子どもだけ」になっている |
当てはまる項目はありましたか?
項目を見てドキッとした方もいるかもしれませんが、
このチェックリストに当てはまっているからといって、
毒親であるわけではありません。
自分の行動の問題点に気がつき、
内省して「どう変わろうとするか」が大切です!

INFPだからできる!健全な親子関係を築く9つのヒント

「毒親」と言わせないために、
INFPは、親として何を気を付ければよいのでしょうか。
ここでは、INFPの親が健全な親子関係を築くためのヒントを9つ紹介します。
- 理想は子どもと一緒に育てていく
- 高い共感力を活かして子どもを見守る
- 感情をコントロールする方法を見つける
- 自身の内向性を調整する
- 逃避意識を変えて子どもと向き合う
- 完璧主義をゆるめて安心感につなげる
- 子どもとの健全な距離を意識して自立を促す
- ぶつかる勇気を持って信頼関係を築く
- INFPらしく愛情表現を工夫する
ヒント①理想は子どもと一緒に育てていく
INFPの親は、自分の理想を子どもに教えるのではなく、
子どもと対話しながら一緒に育てていくことが大切です。
なぜなら、INFPの親の理想は、
子どもに幸せになってほしいという純粋な願いからくるものが多く、
押し付けることがなければ、子どもの成長を促すことができるからです。
たとえば、進路を迷ってる子どもに対しては、
- 無理はしなくていいよ。あなたが納得できるかたちってなんだろう?
- 何になりたいかより、どんな人生を送りたいか考えてみるのもいいよね
など、答えをあげるのではなく、
「自分で考える力」を引き出す声かけをしてみましょう。

子どもとのコミュニケーションですね。
ヒント➁高い共感力を活かして子どもを見守る
INFPの共感力は、感情移入しすぎると逆効果になりますが、
使い方次第では子育ての大きな強みとなります。
子どもの心に寄り添うことで深い理解を示し、
安心感を与えることができるからです。
共感力を活かす大事なポイントを3つ紹介します。
- 子どもの感情を代わりに感じるのではなく、隣に立って見守る
例)「私はそばにいるから大丈夫だよ」 - 察して言い過ぎる前に、子どもに主導権を与える
例)「何か話したいことある?」 - 子どもが苦しんでいるときに、すぐに解決策を与えない
例)「あなたなら乗り越えられると信じているよ」
子どもの感情と自分の感情の境界を意識し、
「感情を言葉にする機会」を与えることが大切です。

親子の信頼関係も築くことができます!
ヒント③感情をコントロールする方法を見つける
INFPの特徴である感受性の強さは、
弱点にもなりますが、子どもを育てる力の資源にもなり得ます。
なぜなら、子どもの感情も理解して受け止めてあげられるため、
子どもと心でつながることができるからです。
大切なのは、自分自身で感情をコントロールする方法を身につけることです。
感情の起伏との付き合い方の例を5つ挙げます。
まずはひとつでも、自分に合った方法を試してみましょう。
- 感情をノートに書き出すなど、言語化して整理する
- ひとりの時間を意識的に設ける
- 不安や悩みを第三者(信頼できる人・カウンセラーなど)に話す
- 感情が強く揺れているときには決断を避けて、30分時間を置く
- 感情に飲まれそうになったら深呼吸を3回する

心に余裕ができ、子どもとの関係をより良好にすることができます。
ヒント④自身の内向性を調整する
INFPの内向性は、
子どもの関係性とバランスを取ることで、
良好な親子関係の構築につながります。
なぜなら、子どもの内面や個性を尊重する姿勢に優れているため、
子どもと信頼関係を築くことができるからです。
バランスを取るためにできることは、
- 子どもの声に耳を傾けて、自分の頭の中にいる時間から意識的に抜け出す
- 子どもには様々な人と出会う機会を与える(自分は一歩引いて見守る)
- 少しでも自分だけの時間を確保して、心の余白をつくる
など、自身の内向性を否定せずに調整することです。

子どもとの見えるつながりを意識すれば「毒親」にはなりません。
ヒント⑤逃避意識を変えて子どもと向き合う
INFPの逃避傾向は、
少し意識を変えるだけで、子どもへの優しさや共感に変えることができます。
なぜなら、逃避傾向はINFPの感受性の裏返しにあるからです。
意識を変えるポイントを4つ挙げます。
- 逃避したい感情を放置せず、心を整える時間を習慣的に持つ
- 何から逃げたくなっているのか、感情を言語化して整理する
- 信頼できる人に悩みを吐き出して、現実への抵抗をやわらげる
- 小さなことでも先に行動を起こして、後から感情を整える

自分の逃げ癖を理解しておくことで、
子どもの問題に親身に向き合うことができるはずです。
ヒント⑥完璧主義をゆるめて安心感につなげる
INFPの完璧主義は、
自身の「こうあるべき」という理想からくることが多いですが、
この理想を完全に捨てる必要はありません。
完璧主義の理想は、子どもへの愛ゆえのものでもあるからです。
ただ、理想を子どもに押し付けることに問題があります。
安心や共感をキーワードに完璧主義を少しゆるめると、
子どもからの信頼感につながります。
例えば、
- 「そんなに頑張らなくても、あなたは大切な存在だよ」
- 「ここがわからないの?私も昔は苦手だったんだ」
- 「うまくいかなくても、あなたがチャレンジしたことがすごいよ」
といった声かけが効果的です。

「そばにいてくれる親」を意識すると、
親子関係も良好になっていくでしょう。
ヒント⑦子どもとの健全な距離を意識して自立を促す
INFPの親は、子どもに依存しないために自身で工夫することで、
親子関係をより良好に保つことができます。
依存する背景には、
子どものことを大切に思う気持ちがあるからです。
依存を抑えるために、具体的にできる工夫を3つ挙げます。
- 感情の境界線を意識する
例)「子どもは子どもの人生を生きている」
「私は代わってはあげられないけど支えてあげることはできる」 - 依存的な愛情表現の言葉を、自立を促す言葉に変える
例)「あなたがいないと生きていけない」
⇒「あなたがいてくれて嬉しいけど、あなたは自分の道を歩いてね」 - 親以外の役割を持って自分の世界を育てる
例)趣味や他の人と関わる時間を意識的に設ける
子どもとの健全な距離を意識して、
子どもと自分を分けて考えるだけで、
重たい愛情から、深い安心感に変えることができます。

ヒント⑧ぶつかる勇気を持って信頼関係を築く
INFPの親が自分の平和主義と健全に向き合うためには、
争いを避けるのではなく、
対立を通じて信頼を深める姿勢が大切です。
子育てには「ぶつかる勇気」と「境界線の明確さ」が
必要になる場面もあるからです。
INFPが対立を恐れないようになる考え方の例を、
状況別に3つ挙げます。
- 衝突を避けたるために話題をそらしたいと思ったとき
⇒お互いの違いを乗り越えることで、親子の絆が深まるチャンスと捉える - 言ったら嫌われるかもしれないとためらうとき
⇒「伝えた方が子どものためになる」と考える - いい親でいようと、怒りや疲れを隠そうと思ったとき
⇒「いま疲れているから、ちょっと休ませて」と少しずつ本音を伝える
平和とは「静けさ」ではなく、
「ぶつかっても大丈夫な信頼関係」にあります。

本当の意味で平和な家庭を目指しましょう。
ヒント⑨INFPらしく愛情表現を工夫する
INFPの口下手は、
持ち前の共感力や思慮深さでカバーすることができます。
瞬発的に話すことは苦手であっても、
時間をかけて言葉を選ぶことは得意だからです。
例えば、無理せずにできるコミュニケーションの工夫方法を3つ挙げます。
- 伝えたいことをメモしておいて、伝えられるタイミングで話す
- アイコンタクトや相槌、触れ合いなど、非言語でのコミュニケーションを活かす
- 話しにくい内容のときは、物語や例え話など、間接的な表現に置き換えて伝える
口下手になってしまうのは、
感情を真剣に扱い、言葉の重みを大切にしている証拠。
話すのが苦手だからこそ、
丁寧に想いを伝えようとすれば、
その姿勢が子どもにとって一番の安心感につながります。

まとめ|自分を省みる勇気を持てば、毒親にはならない
当記事では、
INFPが毒親と言われる理由から、
INFPだからできる子どもとの向き合い方までを、
詳しく紹介しました。
どんなに愛情があっても、
INFPの感受性の強さや理想主義などから、
子どもの自由を狭めてしまうことは、誰にでも起こり得ることです。
しかし、自分が毒親になっていないかと考えている時点で、
すでに子どもとの関係に責任を持って向き合っている証拠。
決して「毒親」ではありません。
INFPの心の深さと優しさを活かして、子どもと一緒に迷い、もがき、
笑い合いながら育てていけば良いのです。

ぜひあなた自身にも向けてあげてください!



 MBTIのタイプ診断に興味を持って、
MBTIのタイプ診断に興味を持って、
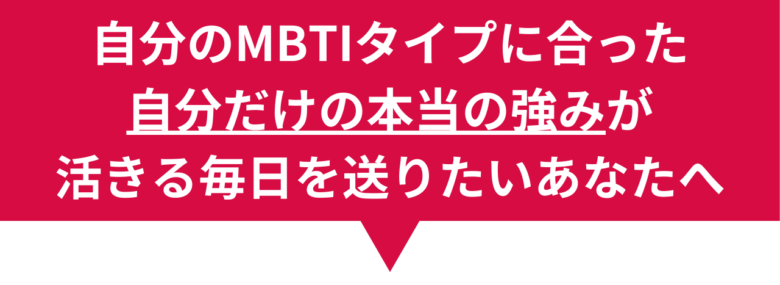














元・社会不適合者ですが、MBTIでわかった自分の強みをフルに活かして起業し、現在は会社経営。
MBTIのタイプ診断をベースに、のべ1000名以上のコンサル・コーチングをしてきました!